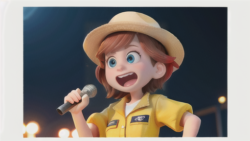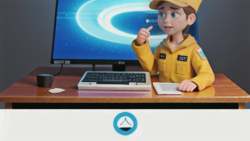救命治療
救命治療 アルカローシス:体の酸と塩基のバランス
私たちの体は、健康を保つために、体の中の酸と塩基の微妙な釣り合いを保つ必要があります。この釣り合いは、血液の酸性度を示す数値(水素イオン指数pH)で測られ、通常は7.35から7.45という狭い範囲に保たれています。この釣り合いが崩れると、様々な健康上の問題が起こることがあります。
アルカローシスは、体の酸と塩基の釣り合いが塩基側に傾き、血液の酸性度を示す数値が7.45を超えた状態を指します。これは、体内で塩基(重炭酸イオンなど)が過剰に蓄積される、あるいは酸(二酸化炭素など)が過剰に失われることで起こります。酸性よりアルカリ性の方が体に良さそうに思われがちですが、釣り合いが崩れると体に悪い影響を及ぼします。適切な酸と塩基の釣り合いは、体内の化学反応を促す物質の働きや、神経の情報伝達、筋肉の収縮など、多くの重要な体の機能に欠かせません。
アルカローシスは、大きく分けて、呼吸性アルカローシスと代謝性アルカローシスに分けられます。呼吸性アルカローシスは、過換気などによって二酸化炭素が過剰に排出されることで起こります。高地への順応ができていない状態で登山すると、酸素不足を補おうとして過呼吸になり、この状態に陥ることがあります。代謝性アルカローシスは、嘔吐や下痢などで胃酸や水分が過剰に失われたり、利尿薬の使用などにより体内の電解質のバランスが崩れたりすることで起こります。
アルカローシスは、放置すると深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、適切な診断と治療が重要です。症状としては、めまい、手足のしびれ、筋肉のけいれん、意識障害などがあらわれます。治療としては、原因となっている病気を治療すること、電解質のバランスを正常化すること、呼吸性アルカローシスの場合は二酸化炭素を体内に補充することなどが行われます。日頃から、バランスの良い食事を摂り、適度な運動をすること、過呼吸にならないように注意することなどが、アルカローシスの予防につながります。