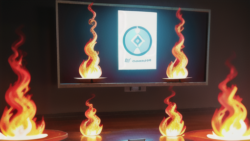緊急対応
緊急対応 放射線障害:知っておくべき基礎知識
放射線による健康への害は、被曝した量や期間、そして影響が現れる時期によって、大きく早期障害と晩発障害のふたつに分けられます。
早期障害は、たくさんの放射線を短時間に浴びた時に比較的早く現れる障害です。主な症状として、吐き気や嘔吐、下痢、倦怠感、発熱、脱毛などが挙げられます。被曝した量が多いほど、これらの症状は重くなります。極めて大量の放射線を浴びた場合には、命に関わることもあります。
一方、晩発障害は、少量の放射線を長期間にわたって浴び続けた場合、もしくは一度に多量の放射線を浴びた数年後から数十年後に現れる障害です。代表的なものとして、がん、白血病、甲状腺機能低下症などがあります。また、放射線被曝によって子孫に影響が出る遺伝的影響も晩発障害の一つです。これらの障害は、放射線が細胞の遺伝子を傷つけることが原因で起こると考えられています。
さらに、早期障害と晩発障害は、被曝線量と症状の出方によって、確定的影響と確率的影響に分類することもできます。確定的影響は、ある一定量以上の放射線を浴びると必ず起きる障害です。例えば、白内障や皮膚の炎症、不妊などが挙げられます。これらの障害は、被曝線量が多いほど症状が重くなります。
確率的影響は、被曝線量が多いほど発生する可能性が高くなりますが、必ずしも起きるとは限らない障害です。がんや白血病、遺伝的影響などがこれに当たります。少量の被曝であっても、これらの障害が発生する可能性はゼロではありません。しかし、被曝線量が少ない場合は、発症確率は非常に低くなります。
このように、放射線障害は様々な形で現れ、その影響は被曝線量や被曝状況によって大きく異なります。そのため、放射線による健康への影響を正しく理解し、状況に応じて適切な対策を講じる必要があります。