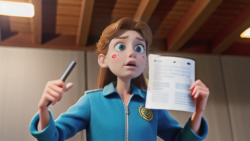救命治療
救命治療 遅延型アレルギーと防災対策
アレルギー反応は、私たちの体が本来無害な物質に対して過剰に反応してしまうことで起こります。この反応には様々な種類があり、大きく即時型と遅延型の二つの型に分けられます。
即時型アレルギーは、原因となる物質(アレルゲン)に触れてから数分から数時間以内という短い時間で症状が現れるのが特徴です。代表的なものとしては、花粉症や食物アレルギー、喘息、じんましん、アナフィラキシーショックなどが挙げられます。これらのアレルギーは、体の中で作られる免疫物質である抗体、特にIgE抗体が重要な役割を果たしています。アレルゲンが体の中に入ると、IgE抗体がアレルゲンと結合し、肥満細胞という細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されます。これらの化学物質が、かゆみやくしゃみ、鼻水、皮膚の発疹といったアレルギー症状を引き起こすのです。迅速な反応であるため、症状の現れ方も急激で、場合によっては生命に関わるアナフィラキシーショックを起こすこともあります。
一方、遅延型アレルギーは、アレルゲンに触れてから24時間から48時間、あるいはそれ以上の時間が経過してから症状が現れます。代表的なものとしては、接触性皮膚炎(金属アレルギーや化粧品かぶれなど)やツベルクリン反応などが挙げられます。即時型アレルギーとは異なり、遅延型アレルギーではT細胞と呼ばれる免疫細胞が中心的な役割を担います。アレルゲンが体内に侵入すると、T細胞がアレルゲンを認識し、攻撃を始めます。このT細胞の働きによって炎症反応が引き起こされ、発疹やかゆみなどの症状が現れるのです。反応までに時間がかかるため、原因となる物質を特定するのが難しい場合もあります。
このように、即時型と遅延型アレルギーでは、反応を引き起こすしくみ、症状が現れるまでの時間、そして症状の種類が大きく異なります。アレルギー症状でお困りの際は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。